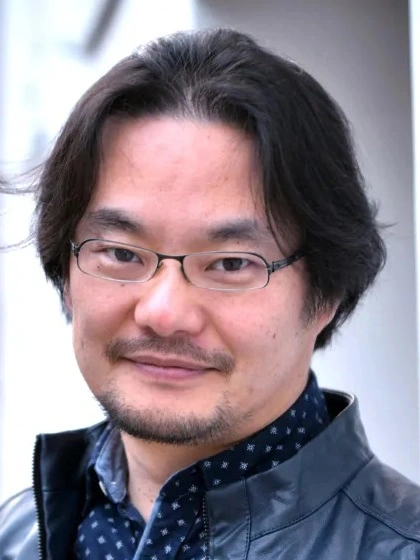ディストピア倫理学:
Dystopia Ethics:
Toward Future Technologies
With Uncertain Self-boundaries
人間の身体や精神に介入し、それらを改変する未来のテクノロジーは、
自己と非自己の境界をどのように変えていくでしょうか。
あるいは、そうした境界がテクノロジーで変えられてしまうようなものであれば、
そもそも「自己の本質」などあったのでしょうか。
本研究領域は、こうした哲学的な問題意識から出発する研究プロジェクトです。
そして、未来のテクノロジーが人間の生き方や社会生活について
どのようなインパクトを持つかを考えるという、
倫理学的な分析を進めるプロジェクトでもあります。
そのために本研究領域では、近づきつつある未来のテクノロジーが自己の変容を
どのように巻き込みうるのか、あえてその破滅的な「ポテンシャル」を探るという、
予見的な分析をしてみようと思います。
そうすることで、私たちにとって大事な生き方がどのようなものだったのかを
明らかにすることができるでしょうし、
それはつまり、私たちの無自覚な価値観を探る試みでもあります。
本研究領域は、4つの研究班から構成されています。
上記のようなアイデアをベースとして、それぞれの班が、異なる角度から、
あるいは異なるテクノロジーをとりあげて、分析を進めます。
そのなかには、未来のテクノロジーに対して悲観的な視点もあれば、
楽観的な視点もあるでしょう。
そうした様々な視点を持ち寄りながら、テクノロジーを通じてもっと自由に、
もっと多様に、もっと自分らしくなれるような、
「テクノロジーを生きる人間」観を追求したいと思います。